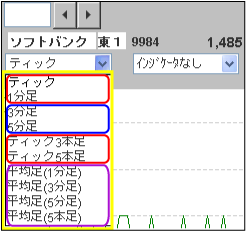
| ● | 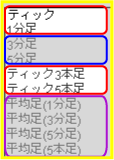 |
赤で囲まれた「ティック」「ティック3本足」「ティック5本足」「1分足」は、比較的値付き度合いの高い銘柄の分析に使います。例えば、1分間(60秒)に60回の値付きがある銘柄の場合、ティック3本足ですと20本のローソク足が、ティック5本足ですと12本のローソク足が描かれますから、1分足・3分足・5分足で描くローソク足1本分の情報より、詳細な値動きの情報に対し、各種インジケータによるテクニカル分析を施すことが出来ます。 |
| ◆ | インジケータのあわせ方 画面上で右クリックします。 次に「設定」を選んで左クリックします。 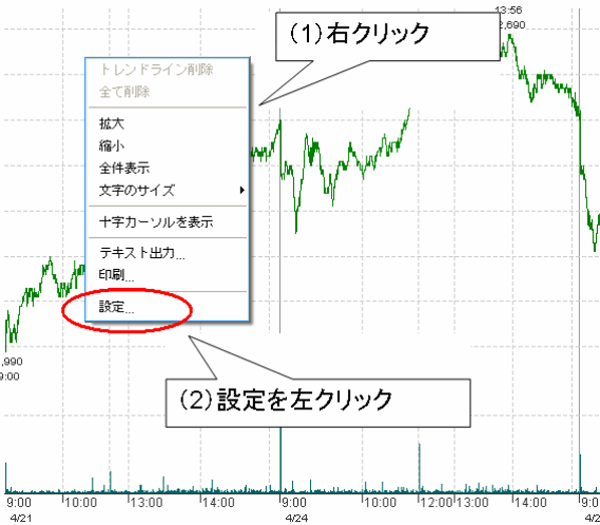 次は、分析したい「パラメータ」を指定します。次に、変更したい「インジケータ」を選び、その数値を変更して「OK」ボタンを押すと、自己流の分析ができます。 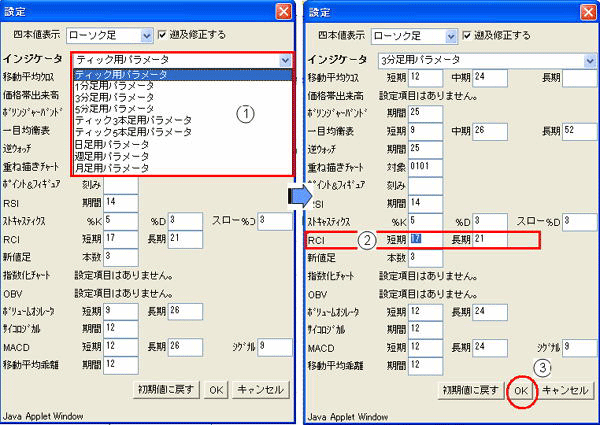 |
| ◆ | 「1分足」での分析は、「ティック」「ティック3本足」「ティック5本足」で分析を必要とするほど激しい値付きではない銘柄の場合で、ただし、1分間でローソク足を描くに必要な値付き(4本)があるような銘柄の分析に利用します。ただ、値付きがない銘柄の場合でも、「短期勝負」を目指す場合のテクニカル分析については、「ティック」「ティック3本足」「ティック5本足」と、「1分足」の利用が有利です。この分析は、転換点ごとに頻繁な売買を繰り返し、小さな利益を積み上げて、トータル利益の最大化を目指します。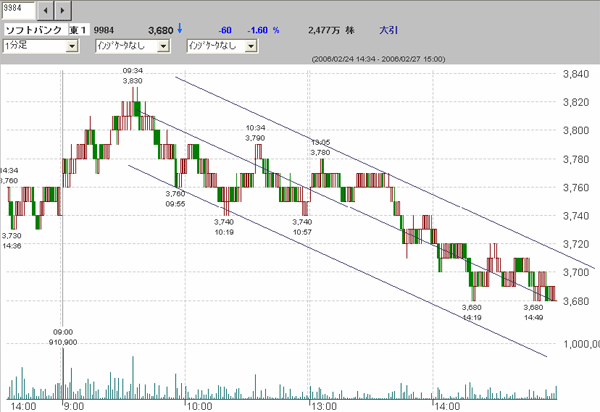 1分足とティック足との違いで注目すべきは、「トレンドライン」の描画です。1分足の場合、横軸が「1分」で一定ですから、トレンドラインを描画し、トレンドの方向性を確認しながら、売買タイミングを探ることが出来ます。ティック足でもトレンドラインは描けますが、横軸の時間が一定ではありませんので、その有効性には疑問が残ります。 |
| ◆ | トレンドラインの描き方 開始場所で「左クリック」し、マウスを押したままの状態で終了場所へと「トレンドライン」を引きます。引いたトレンドラインをドラッグすると「平行線」が引けます。 |
| ◆ | トレンドラインの消し方 トレンドラインにカーソルを合わせた状態で「右クリック」します。最上の「トレンドライン削除」か「すべて削除」で消えます。 |
| ▲ TOPへ |
| ● | 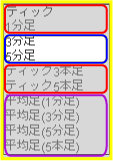 |
青で囲まれた「3分足」「5分足」は、スイングトレード(月曜から金曜日までといった数日間での売買)などの比較的ゆったりした売買を目指す方や、分析対象の値付きがさほど頻繁ではないといった銘柄のテクニカル分析に利用します。この分析の場合、最大11日間の足が表示できることをフルに利用し、トレンドラインを描画し、短期トレンドの始まりから終わりまで、トレンドを取ることで、最大のリターンを目指す方法が有効となります。 |
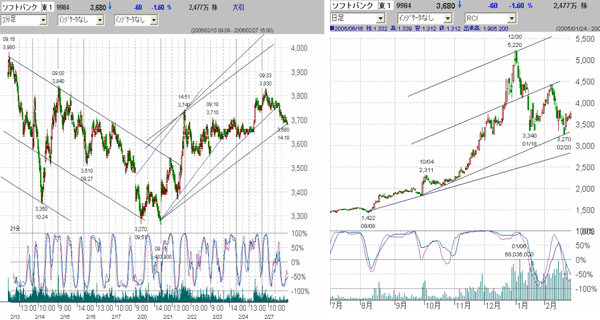 この場合は、日足・週足でのテクニカル分析をまず行うことから始め、大きなトレンドの方向性をつかみ、その流れに沿う形で、基本的なスタンス(売り対象か買い対象か)を決めます。次に、「3分足」「5分足」を利用し、転換点を捉えて仕掛けることになります。 |
||
| ▲ TOPへ |
| ● | 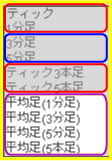 |
紫で囲まれた「平均足(1分足)、平均足(3分足)、平均足(5分足)、平均足(5本足)」は、チャートの方向性(トレンド)の把握が視覚的に判りやすく、FX(外国為替証拠金取引)などの売買で最近注目されている表記ですが、株価チャートにおいても短期的なトレンドが明確に表現される点は同じです。
平均足はランダムな株価の動きを平均化することで、チャートの流れを円滑化させ、トレンド判断の確率を高めようとしたものです。基本的な解釈は、陽線(の連続)が強気相場を示し、陰線(の連続)が弱気相場を示します。実体部分の長さはトレンドの強さを示し、陽線(の連続)→陰線(の連続)、または陰線(の連続)→陽線(の連続)がトレンドの変化を表わします。 |
「平均足(3分足)のチャート表示例」
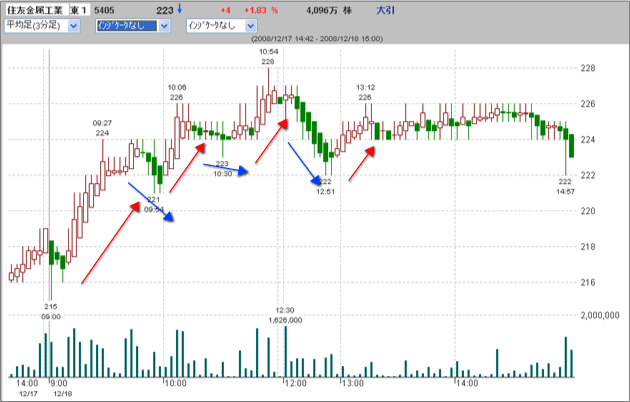 |
| ▲ TOPへ |
(2)インジケータの選び方
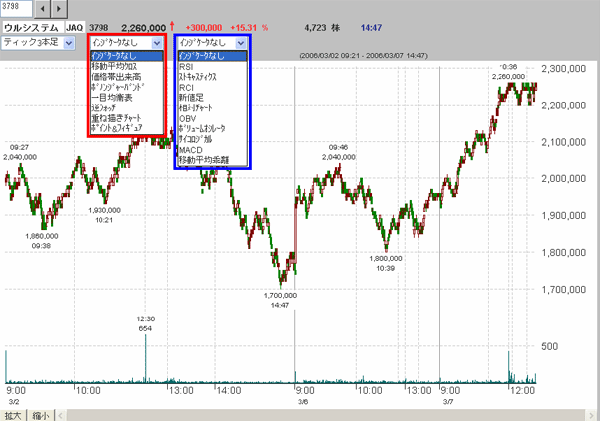
| ● | 赤枠のインジケータは、(A)トレンド系のテクニカル指標と(B)全画面表示のテクニカル指標、(C)その他の指標となります。 画面の上部2/3~全部を使い表示するものが「左側(赤枠)のインジケータ」です。 (A)のものとしては「移動平均クロス」「ボリンジャーバンド」「一目均衡表」があり、(B)のものとしては「逆ウォッチ」「重ね描きチャート」「ポイント&フィギュア」があり、(C)のものとしては「価格帯別出来高」があります。 |
| ◆ | (A)の「移動平均クロス」「ボリンジャーバンド」「一目均衡表」と(C)の「価格帯別出来高」は「右側(青枠)」のインジケータ」と組み合わせることができます。 |
| ◆ | テクニカル分析は、大きく分けて2つあり、「方向性を追うトレンド系」と「変化の様子を見るオシレーター系」に大別できます。トレンド系とオシレーター系を組み合わせたテクニカル分析が有効とされますから、「左側(赤枠)のインジケータ」と「右側(青枠)のインジケータ」組み合わせを持って分析する手法をお勧めします。 |
| ▲ TOPへ |
| ● | インジケータ1のテクニカル分析指標 ■移動平均クロス■ 短期移動平均線が中期や長期の移動平均線を、あるいは中期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜ける動きで交差することを「ゴールデンクロス」と呼びます。逆に、短期移動平均線が中期や長期の移動平均線を、あるいは中期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜ける動きで交差することを「デッドクロス」と呼びます。 「ゴールデンクロス」は下降していた株価が上向きに転じたことを確認するシグナルとして、「デッドクロス」は上昇していた株価が下向きに転じたことを確認するシグナルとして捉えます。 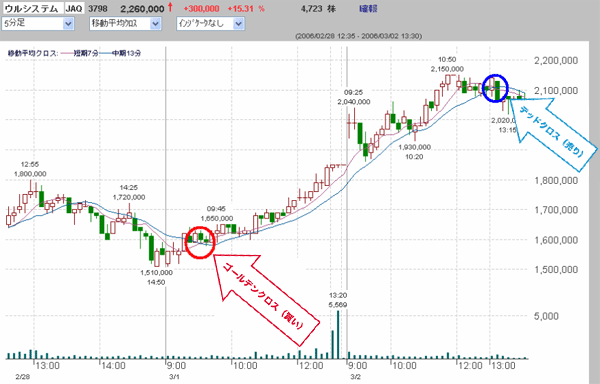
■価格帯別出来高■ 画面左に価格帯別に出来高の棒グラフが表示されます。画面上に表示されている期間分の出来高を、各価格帯に出来高表示したものです。 価格帯の多い部分(出っ張っている部分)は、上昇における上値のシコリが重いところ(下落ではサポートライン)を意味し、少ない部分は値動きが軽いことを意味します。なお、価格帯の幅は表示サイズから自動計算されます。 
■ボリンジャーバンド■ ボリンジャーバンドは、移動平均と標準偏差を用いた株価の分布状況から、株価が「天底」を付けるタイミングを察知します。価格の変動幅が正規分布している場合の1σ(シグマ=真ん中の移動平均線から上下1本のレンジ)内に価格の変動幅が入る確率は約68%、2σ(真ん中の移動平均線から上下2本のレンジ)内に価格の変動幅が入る確率は約95%です。上下2σをどちらかにブレイクする確率はわずか2.5%であり、稀にしか起こりませんから、このタイミングで逆張りを行います。 なお、ボリンジャーバンドは、収束(巾着のように萎んだ状態)した後の拡散(帯が拡大する状態)では、「トレンドの出現」と見ますから、逆張り手法であると同時にトレンド手法でもあります。 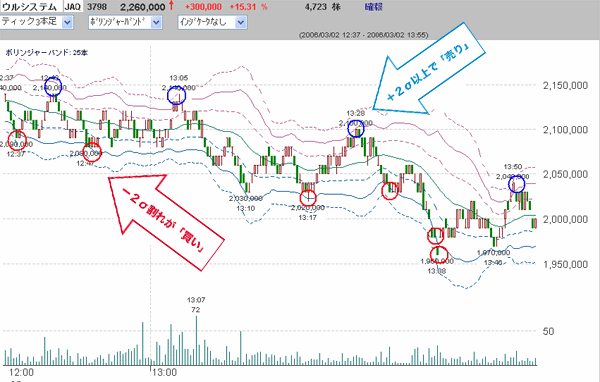
真ん中の線が移動平均線で、その上下の線が+1σと-1σ、移動平均線の2つ上下の線が+2σと-2σ、一番外側の線が+3σと-3σです。
■一目均衡表■ (A)「転換線と基準線の関係」、(B)「価格と遅行スパンとの関係」、(C)「価格と抵抗帯との関係」から大勢的な'トレンドの転換'を見極める指標です。 転換線が基準線を下から上に突破することを「好転」と呼び、上昇場面の到来とします。反対に「逆転」は下落場面の到来を示唆しています。 次に、遅行スパンが株価(足)を下から上に突破したことを「遅行スパンの好転」と言い、逆に、遅行スパンが株価(ローソク足)を上から下に割り込むことを「遅行スパンの逆転」と言い、トレンド確認に利用します。 抵抗帯(雲)とは、先行スパン1、2で形成される帯のことで、この抵抗帯に株価が位置すると進行方向に対して抵抗を示し、いざ株価がこの雲を通過してしまうとなると、その株価が進む方向を支持する側に回るという働きをします。 【描画のルール】 「基準線」 → 長期期間の高値と安値の平均線です。 「転換線」 → 短期期間の高値と安値の平均線です。 「遅行スパン」 → 当日の終値を長期間だけ遡った位置に描画する線です。 「先行スパン1」 → 基準線と転換線の平均値を長期間だけ進めた位置に描画する線です。 「先行スパン2」 → 長期間の2倍の期間において、最高値と最安値の中間値を長期期間だけ進めた位置に描画する線です。 「雲」 → 先行スパン1と先行スパン2に囲まれた領域で、塗りつぶして表示します。 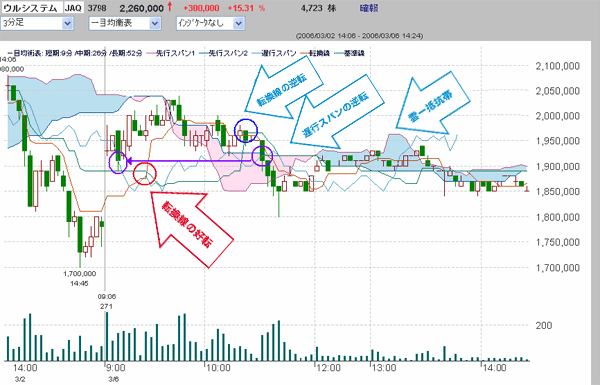
■逆ウォッチ■ 株価(足)のサイクルを8つの段階に分けて説明できるとしたもので、現在の取るべきスタンスの確認に利用します。 1.株価はまだ低位だが、出来高が増加し始め、陽転の兆しと見て買い場を探る。 2.出来高が増え、株価も上昇し、買い信号と見て買う行動に入る。 3.株価はなおも上昇するが、出来高は変わらないので、押し目なら買う。 4.株価上昇の勢いが鈍り、出来高も減少し始め、買いを見送り、噴き値は売る。 5.株価の上昇が止まり、出来高は減少し続け、陰転の兆しに売り場を探る。 6.なおも出来高が減少し、株価も下降し始め、売り信号と見て、売り行動に入る。 7.出来高が低調で、株価も下げている。戻り場面があればすかさず売る。 8.株価は下げ続けるが、出来高に回復の兆し。売りは手控える。 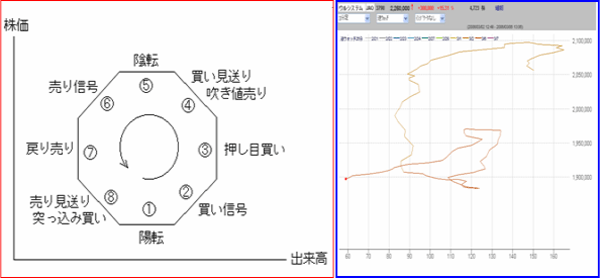
■重ね描きチャート■ 指定の銘柄について、最高値と最安値が重なるように4本値を描画するチャートで、デフォルトでは、「日経平均株価(101)」が赤色にて重ね描きされます。この「重ね描きチャート」は、連動性の高い銘柄、あるいは指数の動きに対し、価格差を確認し、出遅感をからの仕掛けに利用したり、指数との連動性を確認したりするものです。 インジケータ2(右側のインジケータ)の「指数化チャート」と併用して利用しますと、左端が100としてスタートとし、その後の値動き(比率)の割合が、指数化チャートグラフ(画面下方)にて、値動率が確認でき、両者を比較できます。 重ね描きの対象を変更するのは、「右クリック」→「設定」→「分・日・週等のパラメータ決定」→「重ね描き」→「証券コード入力」の手順で行います。 
■ポイント&フィギュア■ P&Fは代表的な不規則時系列分析です。特徴は任意に定めた1枠未満の値動きはトレンドと同じ方向であっても省略し、トレンドに逆行する動きについてはさらに大きなフィルターをかけて排除してしまう点にあります。トレンドに沿った動きを単純化し、転換ルールがやや厳しく反転しにくい性質を持ちます。日々のデータを基にしながら数年間の値動きを非常に単純化して表現することも可能で、大きなトレンドをとらえてポジション管理ができます。 P&Fは、基本的にはトレンドを切り取るための手法ですから、中長期のトレンドフォロワーズ(順張り投資)に向いた手法で、短期投資のコントラリアン(逆張り投資)には向いていないと言えます。 「3枠分」逆行したら転換させる形(3 Points Reversal)で、上昇あるいは下落局面から「3枠分」逆行したら、右隣に行を移し、ピークから1枠下の位置から現在値まで×や○が書き加わります。 
基本的な使い方は、上昇局面では直前の上昇局面の一番上の×を上回って×印が付いた時を「買い(ダブルトップ)」とし、下落局面では直前の下落局面の一番下の○を下回って○印が付いた時を「売り(ダブルボトム)」とします。 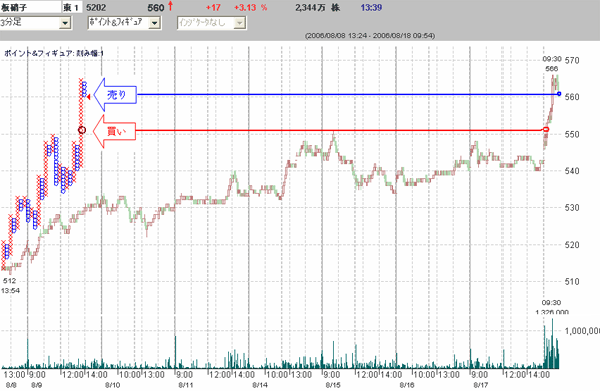
|
| ● | インジケータ2のテクニカル分析指標 ■RSI(相対力指数)■ RSI(相対力指数)は1系列(1銘柄、1指数)の直近の価格により重みを置いた速度です。RSIは0-30%のボトム水準から反発してきたときが「買い」となり、反対に70-100%のポーク水準から版落してきたときが「売り」のタイミングとなります。ただ、上昇トレンドが続いたときや、下降トレンドが続いたときは上限の100%に張り付いたり、下限の0%に張り付いたりしますから、その有効性が低下します。 また、RSIの「示す方向性」を良く見ていると、その後の株価の方向性を予測できることから、その有効性を好む人は多くいます 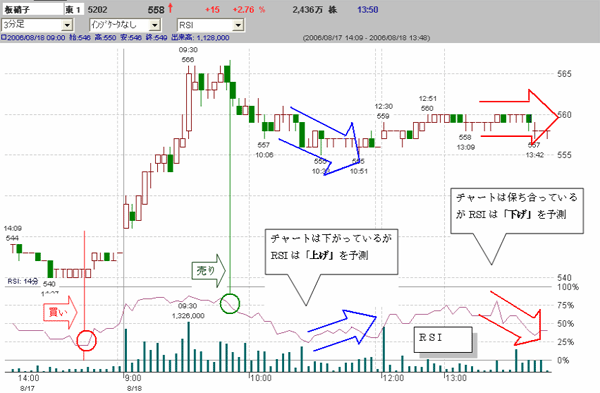
■ストキャスティクス(STC)■ ストキャスティックスにはノーマルな「%K」と3移動平均の「%D」、Slow%Dの3種類の指標が存在します。 現在の株価が最高値に近いのか、最安値に近いのかを示すことで、ストキャスティックスでは「買われ過ぎ」、あるいは「売られ過ぎ」といった「市場の過剰反応」を読み取ることができます。判断基準の目安としては、「80%以上」を高値圏、「20%以下」を安値圏と捉えます。ノーマルな%Kだけでも、80%以上を買われ過ぎとし、20%以下を売られ過ぎとして利用できますが、すぐに100%や0%に達してしまい、レンジにばらつきが生じます。 そのため、%Kより滑らかな動きで、%Kに遅効する3移動平均の%Dと併用します。また、%Kと%Dなど2本の指標のクロスが売買ポイントとなり、株価がある一定のレンジで動いている場合、「押し目買い」や「利食い売り」に効果的です。また、%DとSlow%Dのクロスを売買ポイントとする手法もあります。 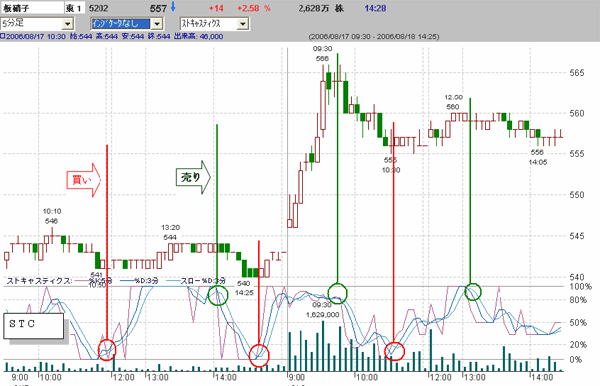
■RCI(順位相関係数)■ RCIは、時間と価格に順位をつけ、その相関関係から売買のタイミングを判断しようとするオシレーター系指標です。RCIは-100から+100までの範囲で変動します。 具体的な利用は、RCIが-100~-60までの水準(ボトム圏)から反発してくれば「買いシグナル」と見なし、逆に+60~+100までの水準(ピーク圏)から反落してくれば「売りシグナル」と見なします。また、RCIを中勢的な強気局面入り、あるいは弱気局面入りの転換点を示唆するシグナルとして活用する時には、RCIが「マイナスからプラスに入ったところ」を「買いのサイン」、「プラスからマイナスに入ったところ」を「売りのサイン」と捉え、仕掛けのタイミングを測ることもあります。 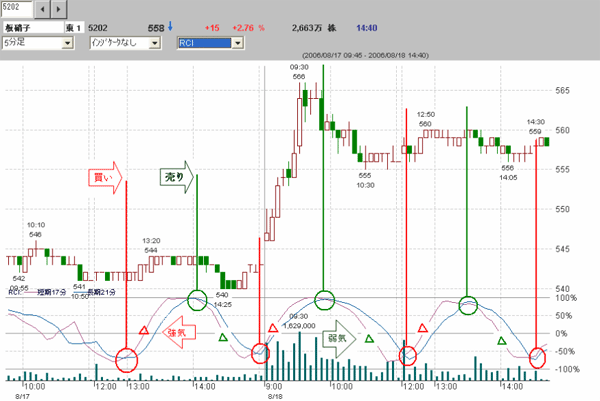
■新値足■ 新値足とは「固定的な値幅」というものがなく、終値が新値(高値、あるいは安値)を更新する度に、チャートの行を変えて足を記入するもので、高値や安値が続いているときは新しい足を次々に引きますが、相場の方向が上昇から下降へ、あるいは下降から上昇へと変化したときには、すぐに足を書き入れるということにはなりません。転換確認の基準は、直前の何本かの足形を上抜く(下降から上昇へ)、あるいは直前の何本かの足を割り込む(上昇から下降へ)タイミングにあります。このことから、新値足は目先の小さな株価変動にとらわれることなく、相場の流れの転換点・売買のタイミングを捉えることに優れた指標といえます。 陽転・陰転はそれだけで相場の転換を示していますが、陽転の場合、その前に続いている陰線の本数が多いほど、その後の反発が見込まれ、逆に陰転の場合は、その前に続いている陽線の本数が多いほど、その時点での株価のピークを示します。 しかし、トレンドの途上で随所に現れる保ち合い局面などでは陽転・陰転が頻繁に出現することになり、「ダマシ」に引っ掛かりやすいという点には注意が必要です。 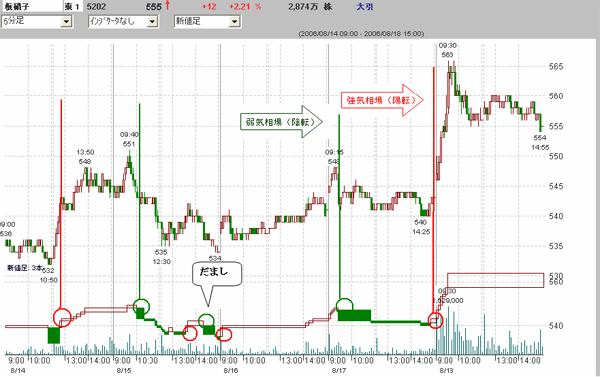
■OBV(オン・バランス・ボリューム)■ OBVとは差し引き計算による出来高を表します。この考え方は、まず出来高を株価上昇時の出来高と株価下落時の出来高に分けます。株価上昇時の出来高は、すべて買いによるものとみなし、株価下落時の出来高はすべて売り方によってもたらされたものと見なします。したがって、それぞれの局面におけるその株価の基調、売買タイミングを判断するには適しますが、半面、大局的にとらえようとする場面では有効性が劣ります。 OBV線が「上昇傾向」にあるときは「買い方の勢力が蓄積」されつつあり、先行き株価上昇が予想されます。「出来高は株価に先行して動く」と云う考え方が基本であり、OBVがトレンドを維持しながら上昇しているときは、買いであり、その逆は売りと判断します。また、ローソク足と同じように前回の抵抗線をブレイクした時も買いとなります。 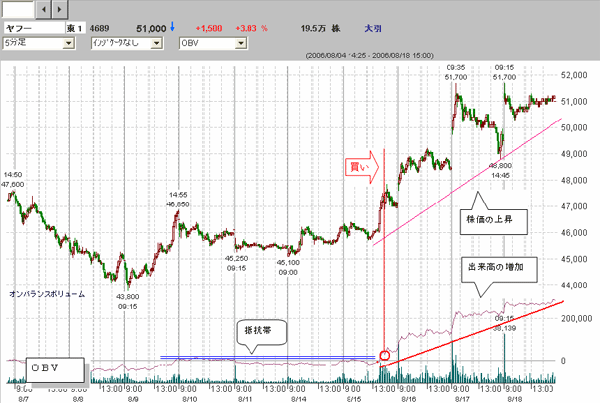
■ボリュームオシレータ■ 計算式は「(短期出来高平均÷長期出来高平均-1)×100」です。短期と長期の出来高平均の差を見て、出来高がトレンドとして増加しているのか、減少しているのかを0ラインの交差で見ます。短期の出来高の急増、急減には不向きで、日・週・月足ベースの長期のタームでの仕掛けどころに利用します。 〇正常 …相場上昇時に、ボリュームオシレーターが上昇傾向である場合です。このときは買いを支持します。また、相場下降時に、ボリュームオシレーターが下降傾向である場合は売りを支持します。 ●異常 …相場上昇時に、ボリュームオシレーターが下降傾向である場合は異常です。このときは取引しないか、逆張りの売りを行います。また、相場下降時も同じです。 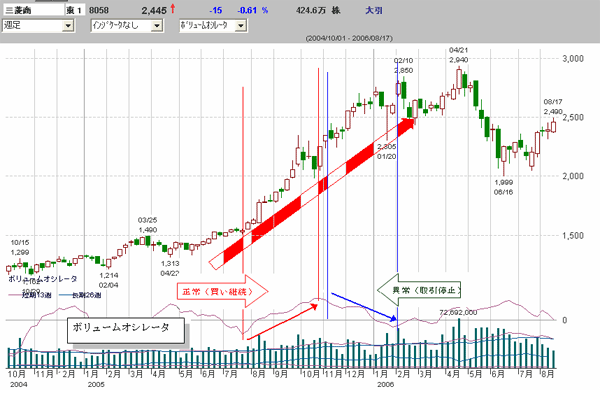
■サイコロジカル■ サイコロジカルとは「心理的な」という意味です。株価の上昇が続けばそろそろ下がるだろう、逆に株価の下落が続けばそろそろ切り返し、上昇するだろうと考える投資家心理を数値化し、市場が強気に傾いた時に売りのタイミングを測り、逆に弱気に傾いた時に買いのタイミングを測る逆バリ手法のオシレーター系指標です。一定期間のうち、株価が前日に比べて高い場面が何回あったかを調べ、その比率を算出します。簡単ながらある程度有効性がある点ですぐれています。 投資家心理は株価の上昇が続けば、ますます強気に傾き、逆に株価の下落が続けば弱気に傾きがちです。市場が強気一色になった時、相場はピークを打ち、逆の弱気一色になった時にボトムを打つケースが多いことから、投資家心理の偏りを数値化した逆バリのための指標です。 ○75%以上(12本間の内9以上がプラスの日)……警戒ゾーン ○25%以下(12本間の内9以上がマイナスの日)……底値ゾーン 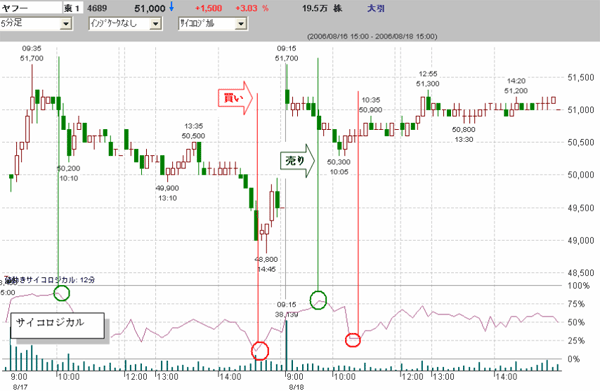
■MACD■ MACDとは「Moving Average Convergence and Divergence」の頭文字をとったものです。この手法は日本語では「移動平均収束発散(拡散)法」又は「移動平均収束乖離」などと呼ぶのが一般的です。その使い方は以下です。 ①MACDとシグナル(MACDの移動平均線)のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り ②上記ゴールデンクロス後、2線ともゼロを上回れば本格上昇 この他に、株価の動きと照らし合わせることで「トレンド転換の予兆」を察知できるという点に同指標の大きな特徴があります。 (A)株価が上昇し続けているのに、MACDが下方に向かうないしはMACDラインのトップを切り下げる→「発散売り」:下落を示唆 (B)株価が下落し続けているのに、MACDが上昇に向かうないしはMACDラインのボトムを切り上げる→「発散買い」:反騰を示唆 (C)株価が上昇に向かう、MACDも上昇に向かう→「収束買い」:上昇トレンド入りの確認、ロングポジションを示唆 (D)株価が下落に向かう、MACDも下落に向かう→「収束売り」:下降トレンド入りの確認、ロングポジションの決済を示唆 具体的には、価格が局所的な高値を更新しているにもかかわらず、MACDがピークをつけ、ダウントレンドに入った場合、価格の下落を予想し、それに見合ったポジションを構える。逆に、価格が局所的な安値を更新しているにもかかわらず、MACDがボトムをつけてアップトレンドに入った場合は株価の反転・上昇を想定して対処するという使い方が有効です。 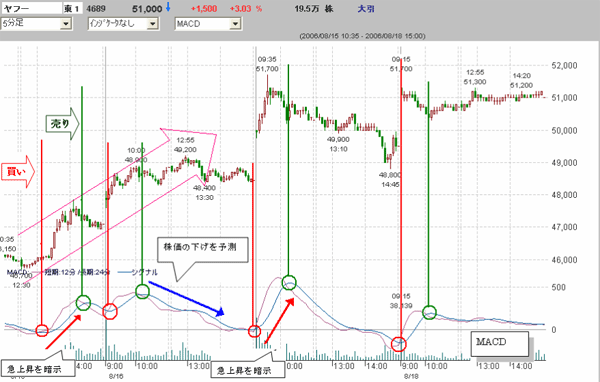
■移動平均乖離■ 移動平均線乖離とは、株価が移動平均線に対してどれくらい離れているか(乖離しているか)を見るものです。移動平均線そのものは、株価が近づいたときに転換点や方向性を見る指標といえますが、この移動平均線乖離率は、株価が平均線から離れたときに利用する指標といえます。ここでは移動平均線が上昇中か下降中かは考慮せず、株価と平均線の乖離率だけを問題にします。 移動平均線乖離率は、「移動平均線に対する大幅な株価の乖離(上方・下方)はやがて修正される」という経験則に基づき、相場の行き過ぎ(株価の上げ過ぎ、下げ過ぎ)をチェックするのに有効です。 インジケータ1に「移動平均クロス」を設定し、移動平均乖離と併用するのが有効でしょう。 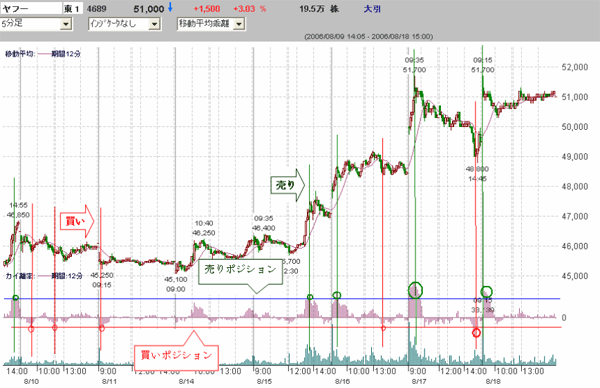
|