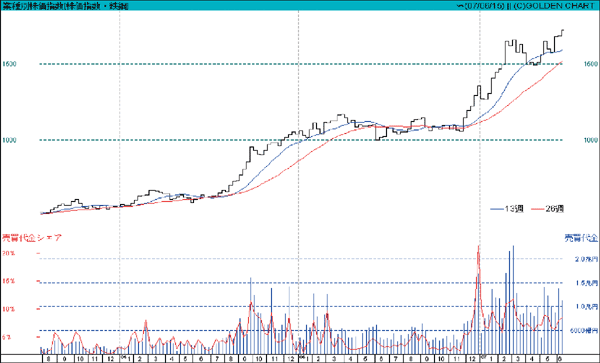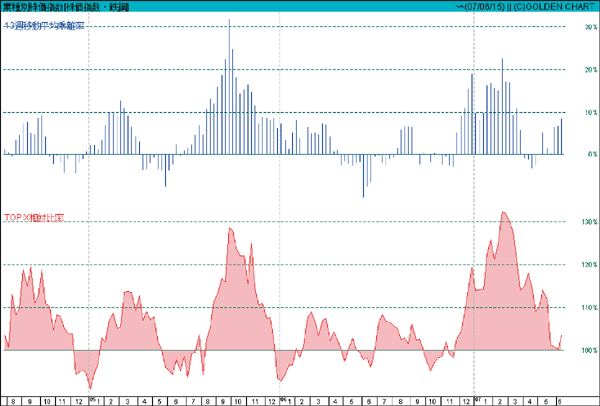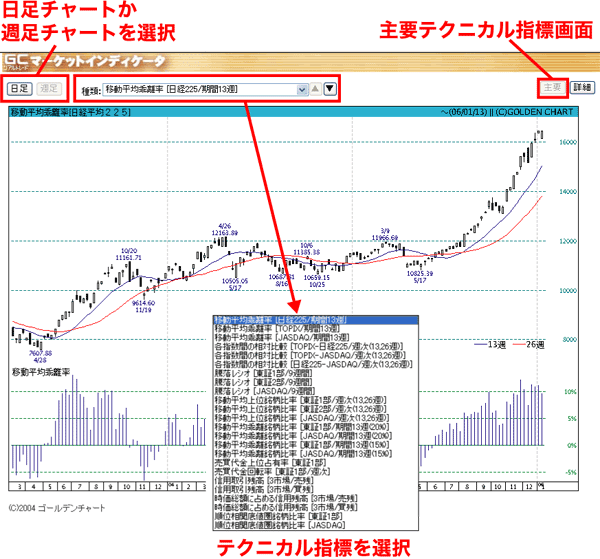
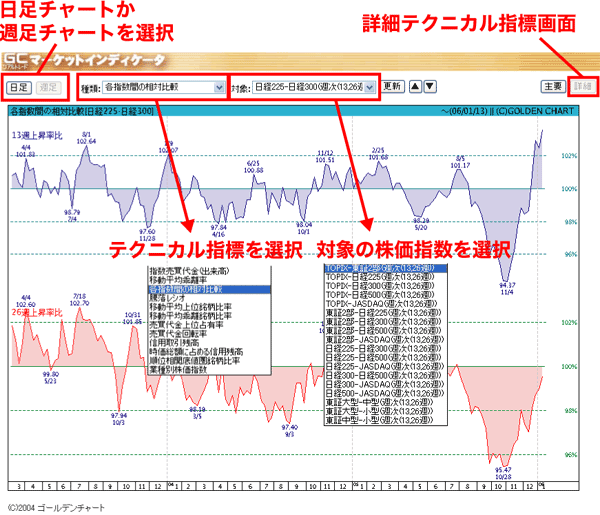
・各指標の概要
①移動平均乖離率
移動平均乖離率は、株価指標が移動平均線からどの程度離れているか、その乖離を表わしたものです。移動平均線は、その計算期間の平均買いコスト、売り建てている場合は平均売りコストと置き直すことができます。移動平均乖離率は平均買い(売り)コストからの離れ度合いを表わし、買いの場合は、上方に大きく離れると利食いの売りが入り、大きく下方に離れると、ナンピン買いや新規の買いが入ることが予想されます。
上記は一般的な説明になりますが、注意が必要なのは、大きく離れるのは上昇ピッチや下落のピッチが速いためで、時間をかけて株価が動いている時には、移動平均線もゆっくり動くので、乖離は大きくはなりません。移動平均乖離率は急ピッチな株価変動に行き過ぎがないかどうかをチェックする指標と、置き直した方がわかりやすいでしょう。
どちらにしても、あまり速いピッチでの上昇・下落は解消されるはずで、乖離率そのものは平均的な水準へ回帰します。平均的な乖離率の回帰は、株価が変動して移動平均線に接近すること、あるいは株価の変動がその水準で小幅にとどまり、計算上移動平均線が株価に接近することによりますが、どちらにしても大きく乖離したところはリスクテイクしていい水準といえるわけです。
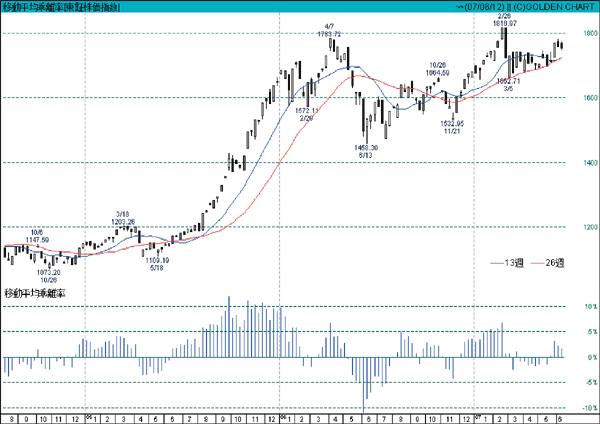
このチャート例では、乖離率の7%以上が弱いメド、10%以上が強いメドとなっています。
②各指数間の相対比較
各指数間の一定期間のパフォーマンスを比較することによって、各指数や大型・中型・小型株のアンバランスを捉えようとするものです。各指数は、その指数を構成する銘柄群の特徴を代表するので、指数を比較することによって得られる情報は数多くあります。
指数間の相対比較は、中でもとりわけTOPIX-日経平均225、東証大型株指数-小型株指数などが、マーケットにおける物色の流れの変化を捉えるという観点から注目されます。
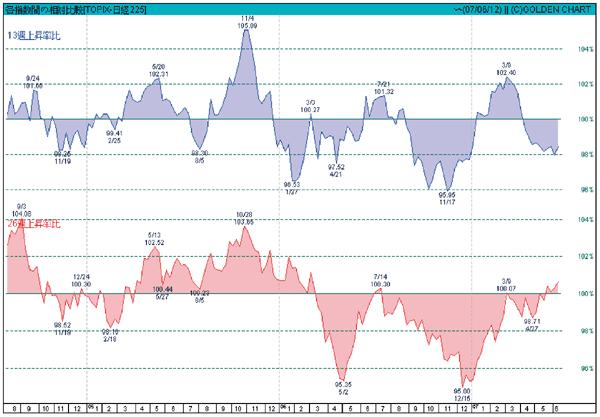
TOPIX-日経平均225の相対比較例です。
グラフが上昇している時はTOPIX(前者)が優位の展開、
下方に向かっている時は日経平均225(後者)が優位、
13週比較でみると、100%を中心に±5ポイント程度で転換することが多くなっています。
③騰落レシオ(9週)
騰落レシオは、一定期間の値上がり銘柄数の合計を、同じく値下がり銘柄数の合計で除したもので、マーケットの強弱を測る一般的な指標として認識されています。9週騰落レシオは、まず週間ベースで値上がり銘柄数、値下がり銘柄数を計算し、9週間分合計して除算すれば、算出できます。
9週騰落レシオは60%割れで、マーケットはボトム圏とみなすのが一般的で、反対に150%を超える水準では、マーケットの物色が広がりすぎて、その後は物色対象を絞る動きに入ることが多くなります。
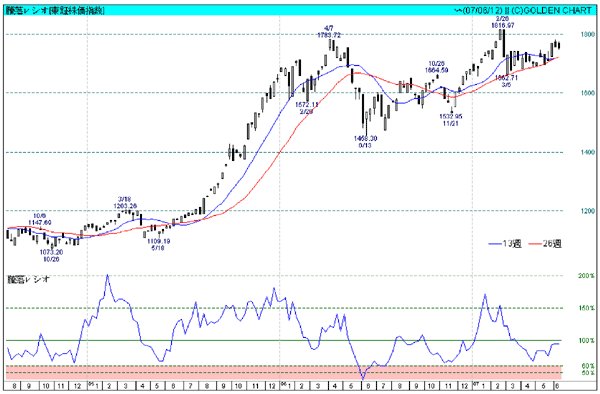
9週騰落レシオの60%は、9週間の合計で上昇した銘柄数が37.5%、
下落した銘柄が62.5%の局面と捉えれば、わかりやすくなります。
④移動平均上位銘柄比率
移動平均上位銘柄比率は、移動平均線より上位にある銘柄の割合を計算して、どちらかと言えばマーケット全体の底入れを捉えようとする指標です。東証1部や新興市場など、市場別に見た方が、マーケットを把握しやすくなります。
週ベースでは、13週、26週ともに20%割れがボトム圏を示唆しますが、13週は30%割れ、26週は20%割れに基準を置くのが現実的です。反対に、80%超えになると過熱感が出ている水準との見方もありますが、この指標は天井圏での動きが長く、ターニングポイントの確認は単純なものではないことには注意が必要です。下げは同時に、上げは循環物色で時間をかけて--というマーケット特有の動きを反映するからです。
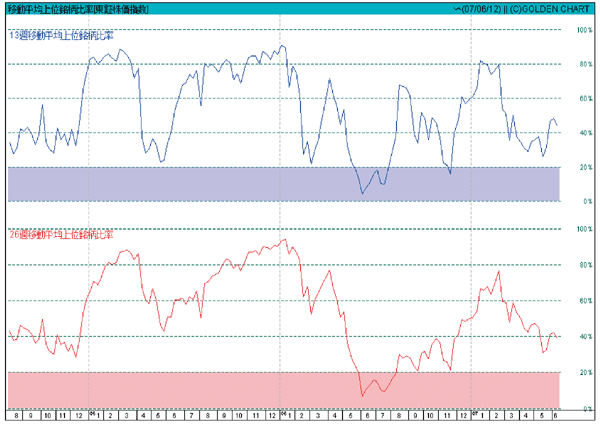
日次では25日、75日、週次では13週、26週が一般的ですが、
週次で中・長期の波動をみる方がフィットしているようです。
⑤移動平均乖離銘柄比率
移動平均乖離銘柄比率は、④移動平均上位銘柄比率を発展させたマーケット指標です。より強烈な天・底であるかどうかは、移動平均線からの乖離が一定基準を超えた銘柄数で捉えた方がより正確という観点から、乖離率を区分して構成比を見ることにより、全体の過熱感や人気の離散度を明確化したものです。
ここでは、13週、26週移動平均線について各々±15%、±20%を超える銘柄数の比率を計算しています。
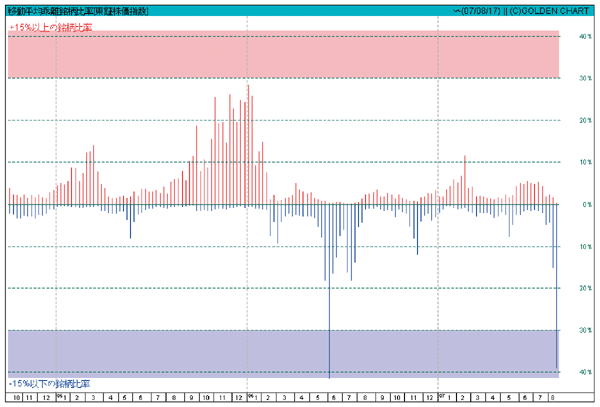
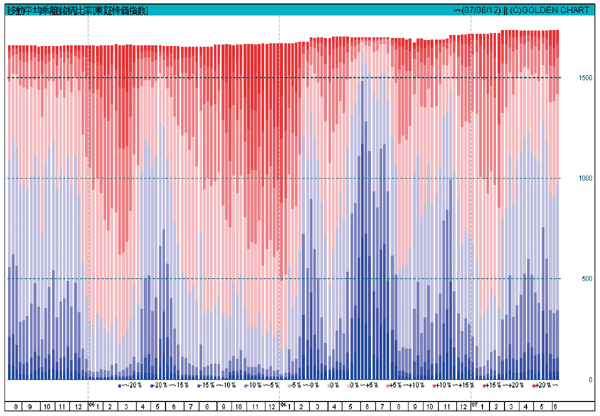
移動平均線からの乖離率を5%のレンジで区切り、
赤の濃い部分は上方に大きく乖離、
青の濃い部分は下方に大きく乖離した銘柄数を示したものです。
⑥売買代金上位占有率
売買代金上位占有率は、上場各社の売買代金を計算し、市場の上位10社、20社、30社にどの程度の商いが集中しているかをトレースしたもので、相場の天・底を捉えるための指標ではなく、物色の集中度をみる指標です。物色の範囲が多岐にわたり、焦点がボケたマーケットは上昇する迫力に欠け、過度に一部の銘柄(群)に人気が集中すると、その後に循環物色に入る可能性は小さく、調整局面が近いといわれています。
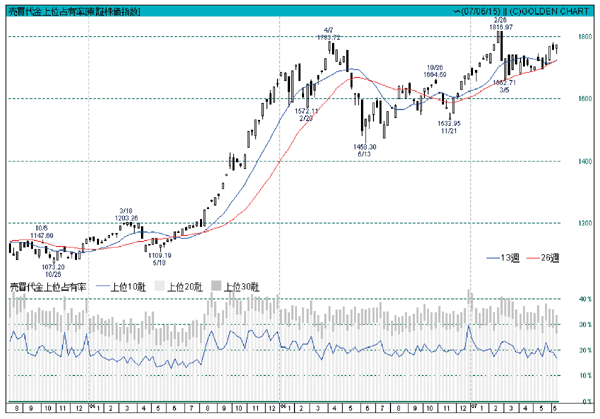
東証1部の過去の経験からは、
売買代金上位30社の占有率が40%を超えてきたケースや、
上位10社で30%を超えてきたケースなどが、マーケットの行き過ぎのメドとなりそうです。
⑦売買代金回転率
売買代金回転率は、出来高回転率と同様のボリューム指標で、マーケット全体の過熱の度合いをチェックします。出来高ではなく、売買代金を使うのは、値がさ株が商いの中心となっているマーケットでは、ボリュームを金額ベースで見ないと過少に認識することになるので、これを修正するためです。
従来は1.0倍超えが過熱シグナルを出すメドでしたが、最近では短期的なシグナルを出す水準として、弱い過熱ラインを1.5倍超え、強い過熱ラインを2.0倍超えと捉えて、機敏な対応が求められるケースも出てきました。
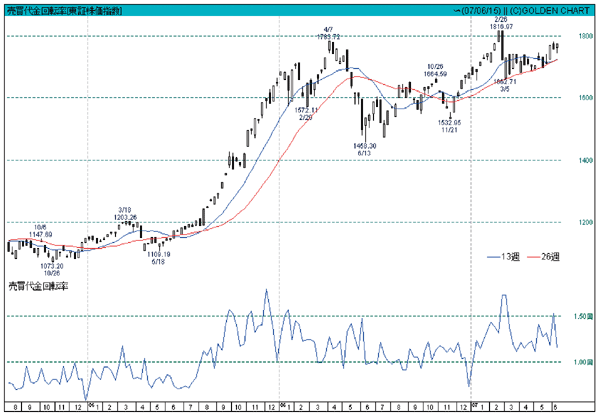
売買代金回転率は過熱局面での重要な指標ですが、
天井圏は底値圏に比べると比較的時間が長いので、
タイミングを捉えるのが難しいのが短所です。
⑧信用取引残高
日経平均やTOPIXでマーケット全体の動向を認識するのと同じように、三市場(東証・大証・名証)ベースの信用取引残高をチェックすることで、仮需の側面からマーケットの動向を認識することができます。
・信用買い残高/売り残高……信用買い残は株価の上昇期待が膨らむことによって増加し、反対に売り残は株価の下落を見込む向きが膨らむことで増加していきます。また、株価の上昇過程では、買い残の増加と同時に、先行きの株価下落を見越した向きからの信用売りも多くなり、商いのボリュームが次第に膨らんでいきます。
マーケットで商いが活発に行われている局面で、買い残が増加傾向で、売り残が減少傾向にあれば、全体相場は株価上昇ムードとなります。反対に、買い残が減少傾向で、売り残が増加傾向にあれば、全体相場は弱気局面への移行が想定されます。また、買い残のピークから6カ月後は、マーケット全体の期日明けとして認識されます。
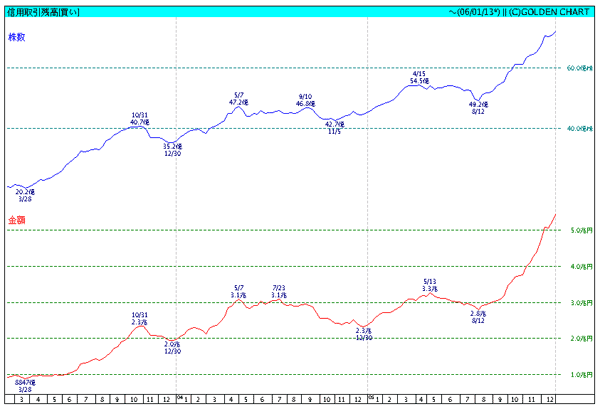
・評価損率……評価損率は、全体の買い残(金額ベース)に対する評価損の割合を示したものです。評価損率が大きくなると全体軟調な局面、小さくなると強気局面と認識されます。一般的には20%以上(グラフでは下方)が底値圏、ゼロ水準接近からマイナス圏(グラフでは上方)が警戒圏を示します。
グラフ下段の倍率(貸借倍率=全体の買い残÷売り残)は、底打ちから上昇(買い残が増加傾向、売り残が減少傾向)してくると、全体相場は株価上昇ムードとなります。反対に、天井を打って反落(買い残が減少傾向、売り残が増加傾向)してくると、全体相場は弱気局面への移行が想定されます。
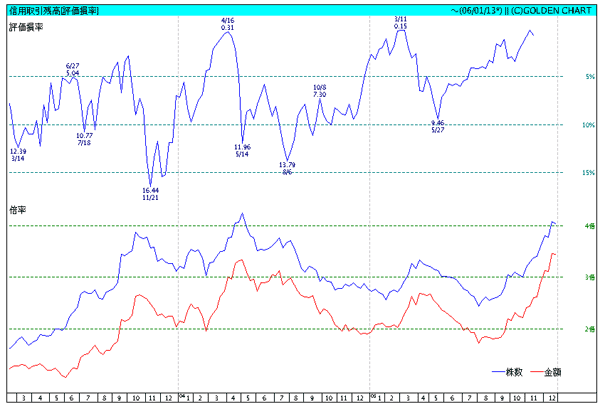
⑨時価総額に占める信用残高
売り残金額、買い残金額の時価総額に対する割合を示したものです。信用残の金額そのものの水準ではなく、時価総額に対する割合を見ているのがポイントで、マーケットの規模に応じた信用取引残の水準を判断します。売り残の時価総額に占める割合もトレースしていますが、どちらかといえば時価総額に占める買い残金額の割合を見ることが多い指標です。
時価総額に占める買い残金額の比率が高くなるケースは、信用取引の買いが通常の状態と比べて多くなっているためで、これはマーケットに参入している投資家の仮需が多く、また、強気に大きく傾いていることを示しています。加えて、先々の返済の売り圧力も同時に大きくなっていることを示しているので、過熱指標として有効です。最近15年間では、1.0%を超えてくると警戒ラインと認識されています。
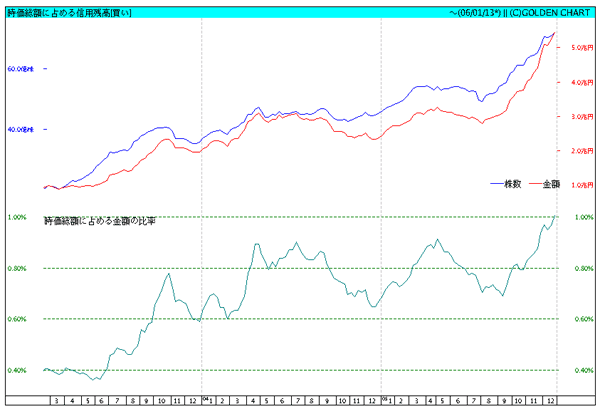
⑩順位相関底値圏銘柄比率
順位相関係数(RCI)は、日柄から見て売買のタイミングを表わす指標です。計算方法は、一定期間の株価に順位を付け、それと日付の順位とどの程度連動するかを計算します。例えば9週RCIでは、9週間連続して株価が高くなれば1(テクニカルな指標としては一般に100を乗じて100で表わします)、少し順番が入れ替わっている場合は80や90などとなります。反対に9週間連続して下落すればマイナス1(テクニカル指標としては▲100)と表わします。
順位相関底値圏銘柄比率は、各市場の上場銘柄を対象に、RCIが▲85-▲100の値を取っている銘柄数を集計し、この銘柄数がその市場の30%を超えてきた時に底値圏、ターニングポイントに近いとみなします。
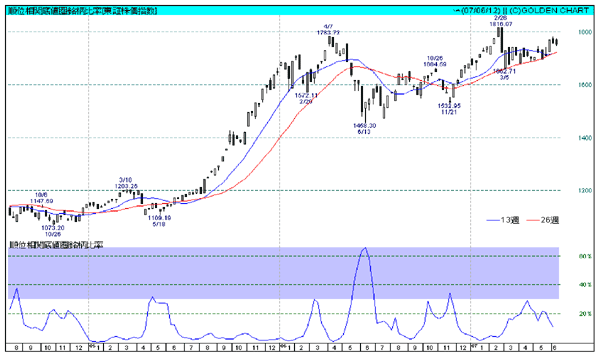
RCIは天井を付けた後、方向転換するタイミングや、
ボトムゾーンを離脱するタイミングを捉える時に有効なテクニカル指標です。
この底値圏銘柄比率は、RCIの特性を活かして
マーケットの底値圏を探る指標となっています。
⑪業種別株価指数
ここでは、東証が公表する業種別指数の動きを、日次と週次で収録しています。週次ベースでは、①指数の動きと売買代金シェア、②13週移動平均線からの乖離率と、対TOPIX相対比較、③26週移動平均線からの乖離率と、対TOPIX相対比較――の3画面から、各セクターの行き過ぎを計ります。中でも、移動平均乖離率と対TOPIX相対比較は、そのセクターの持つ過去の行き過ぎ水準がターニングポイントになることもあって、参考にしていただきたい指標です。